塩分取りすぎ体のSOS
塩分は、あなたの健康を蝕む「静かなる殺人者」かもしれません。

「健康診断で血圧が高いと指摘されたけど、特に自覚症状もないし大丈夫だろう…」
そう思っていませんか?
もし、あなたが日頃から、
- 麺類のスープを全部飲んでしまう
- 醤油やソースをたっぷりかけてしまう
- コンビニや外食に頼ることが多い
といった習慣があるなら、あなたの体は気づかないうちに、静かに、そして確実にダメージを受けているかもしれません。

岐阜県民の7割が「塩分」と「野菜」が足りていない!?
県民の約7割が食塩を摂りすぎています。
特に、男性は1日あたり9.7g、女性は8.6gと、いずれの年代も目標量を上回っています。食塩の摂りすぎは高血圧の原因にもなるため、注意が必要です。食塩摂取量の約7割は調味料から来ているため、減塩調味料を活用したり、かけすぎに注意したりするなど、日々の調理法や食べ方の工夫が大切です。
食塩の目安は男性7.5g未満、女性6.5g未満が目安になっています
塩分取りすぎ体のSOS
第1章:なぜ塩分を減らさなきゃいけないの?
「塩分を摂りすぎると、高血圧になる」
これはよく聞く話ですよね。

でも、「なぜそうなるのか?」まで理解している人は少ないかもしれません。 私たちの体は、体内の水分や塩分の濃度を一定に保つようにできています。塩分を摂りすぎると、体は塩分濃度を下げるために水分を溜め込もうとします。
この「水分を溜め込む」という現象が、血管の中で起こるとどうなるでしょうか? 血管の中を流れる血液の量が増え、パンパンに膨らんでしまいます。
例えるなら、細いホースに大量の水を流すようなものです。ホースにかかる圧力が強くなるのと同じように、血管にかかる圧力、つまり「血圧」が上がってしまうのです。
この状態が続くと、血管は常に強い力にさらされ、次第に硬く、もろくなっていきます。これが「動脈硬化」です。 そして、この動脈硬化こそが、私たちの命に関わる様々な病気の引き金となります。
第2章:あなたの日常に潜む「隠れ塩分」のワナ
「私は料理の味付けを薄くしているから大丈夫!」
そう思っているあなた。本当に大丈夫ですか? 実は、私たちが気づかないうちに、たくさんの塩分を摂ってしまっているケースがほとんどです。
<とある夫婦の1日を例に見てみましょう>
健康診断で血圧が高めだと指摘されたばかりのケンタさん と健康に気を使い始めているアヤさん1日を例に見てみましょう
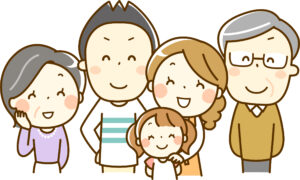
【朝の食卓でのやりとり】
ケンタさん:「今日の朝食、なんか味が薄くないか?醤油をかけてもいいか?」
アヤさん:「待って待って!今日の味噌汁、出汁をしっかり取って塩分控えめに作ったの。それに、昨日の夜、塩鮭を食べたじゃない?それにも結構塩分が入ってるんだよ。」
【解説】 塩鮭や干物、ハム、ベーコンといった加工品には、保存性を高めるために多くの塩分が含まれています。一見ヘルシーに見える食品にも、意外な落とし穴があることを知っておく必要があります。
【お昼休憩でのやりとり】
ケンタさん:「今日もコンビニか。手っ取り早く、カップ麺とサンドイッチにしようかな。」
アヤさん(メッセージ):『カップ麺には、スープまで飲むと1日の塩分目安量を軽く超えちゃうんだって。スープは半分残すか、具だけ食べるようにしてみて!サンドイッチのハムやチーズにも気をつけてね。』
【解説】コンビニや外食は、手軽で便利ですが、塩分が高くなりがちです。特に、カップ麺のスープ、インスタント食品、レトルト食品、そしてドレッシングやソースにも、たっぷりの塩分が含まれています。
【夕食の買い出しでのやりとり】
ケンタさん:「今日の夕食、何にする?惣菜コーナーの唐揚げにしようか。家で作るより美味しいし楽だろ?」
アヤさん:「今日は時間があるから、おうちで唐揚げを作ろうよ!市販のタレを使わずに、下味をつけすぎなければ、塩分をグッと減らせるよ。それに、唐揚げの衣にも塩分が含まれてるから、そこも注意しないとね。」
【解説】 惣菜や外食の料理は、美味しく感じさせるために塩分が多めに使われていることがほとんどです。自炊することで、塩分量をコントロールできるだけでなく、栄養バランスも整えやすくなります。
第3章:塩分の摂りすぎが引き起こす病気の症状とリスク
塩分過多がもたらす病気は、高血圧だけではありません。 ここでは、具体的な病名とその症状について見ていきましょう。
1.高血圧 ・症状: 初期は自覚症状がほとんどありません。「サイレントキラー(静かなる殺人者)」と呼ばれる所以です。 ・リスク: 放置すると、動脈硬化が進行し、次の病気へと繋がります。
2.心臓病(心筋梗塞、心不全など) ・症状: 階段を上るだけで息切れがする、動悸がする、胸が締め付けられるような痛みがある、足のむくみがひどい、といった症状が現れることがあります。 ・リスク: 高血圧により、心臓が常に強い力で血液を送り出すことを強いられ、心臓の筋肉が厚くなり、やがて機能が低下します(心不全)。また、動脈硬化で血管が詰まると、心臓に血液が届かなくなり、心筋梗塞を引き起こします。
3.脳卒中(脳梗塞、脳出血など) ・症状: 手足の麻痺、ろれつが回らない、片側の顔が下がる、急なめまいや視覚障害、激しい頭痛など。これらの症状が突然現れたら、すぐに救急車を呼ぶ必要があります。 ・リスク: 脳の血管が詰まったり(脳梗塞)、破れたり(脳出血)することで起こります。高血圧は、脳の血管に大きな負担をかけ、このリスクを高めます。
4.腎臓病 ・症状: むくみ、だるさ、尿の泡立ち、貧血など。 ・リスク: 腎臓は、体内の余分な塩分や水分を尿として排泄する重要な役割を担っています。塩分を摂りすぎると、腎臓に大きな負担がかかり、その機能が低下します。腎臓の機能が一度低下すると、元に戻すことは非常に難しいとされています。
これらの病気は、どれも私たちの生活の質(QOL)を著しく低下させ、最悪の場合、命を奪うことにもなりかねません。
第4章:今日からできる!塩分を減らすための具体的な工夫
「塩分を減らすのは難しい…」と感じている方も多いかもしれません。でも、ご安心ください。ちょっとした工夫で、無理なく楽しく塩分を減らすことができます。

1.「だし」を味方のしよう! 昆布、鰹節、煮干し、椎茸などから取る「だし」は、うま味の宝庫です。だしのうま味を効かせることで、塩分が少なくても満足感のある味付けになります。市販の顆粒だしも便利ですが、塩分が含まれているものもあるので、原材料表示を確認しましょう。
2.香辛料やハーブ、酸味をうまく使う しょうが、にんにく、カレー粉、わさび、コショウなどの香辛料や、パセリ、バジル、オレガノなどのハーブは、料理の風味を豊かにしてくれます。また、レモンや酢などの酸味も、塩分が少なくても味にメリハリをつけてくれます。
3.「かける」ではなく「つける」 醤油やソース、ドレッシングは、料理全体にかけるのではなく、小皿にとって「つける」ようにしましょう。これだけで、使用する量がぐっと減ります。
4.加工食品は「塩分量」をチェック ハム、ソーセージ、かまぼこ、練り物、そしてパンなど、意外な食品にも塩分が含まれています。購入する際には、栄養成分表示の「食塩相当量」を確認する習慣をつけましょう。
5.減塩タイプの商品を活用する 醤油、味噌、ドレッシングなど、多くの食品で「減塩」タイプが販売されています。これらを賢く活用するのも一つの手です。ただし、減塩タイプだからといって使いすぎると意味がありません。

素朴な疑問
Q1:全く塩分を摂らないと、体に悪影響はありますか?
A1: はい。塩分(ナトリウム)は、細胞の機能維持や神経伝達に不可欠なミネラルです。全く摂らないと、脱水症状やめまい、倦怠感を引き起こす可能性があります。重要なのは「過剰に摂らない」ことであり、「全く摂らない」ことではありません。厚生労働省が推奨する1日の食塩摂取量の目標量は、成人男性7.5g未満、成人女性6.5g未満です。
Q2:汗をかくと塩分が失われると聞きました。運動後は塩分を多めに摂った方がいいですか?
A2: 大量の汗をかいた場合は、水分と同時に塩分も失われるため、熱中症予防のためにも適度な塩分補給は重要です。しかし、スポーツドリンクや塩飴には、予想以上に多くの塩分が含まれていることがあります。軽度の運動であれば、水分補給だけで十分な場合がほとんどです。長時間の運動や炎天下での活動時には、塩分を含む水分をこまめに摂ることが推奨されますが、過剰な摂取は避けましょう。

Q3:減塩生活を始めたら、味が物足りなく感じます。どうすれば慣れますか?
A3: 舌が濃い味に慣れているため、最初は物足りなさを感じるかもしれません。しかし、だしのうま味や香辛料、ハーブなどを活用することで、味の満足感は上がります。また、舌は3ヶ月ほどで新しい味に慣れると言われています。焦らず、少しずつ塩分を減らしていくことが大切です。
Q4:外食が多いのですが、どうやって塩分を減らせばいいですか?
A4: 麺類の汁は残す、小皿に分けてタレをつける、ドレッシングはかけすぎない、定食ならご飯や味噌汁の量を調整する、といった工夫が有効です。また、ラーメンやうどん、丼ものよりも、焼き魚定食や刺身定食を選ぶなど、メニュー自体を意識することも重要です。

Q5:減塩調味料は本当に効果がありますか?
A5: 減塩調味料は、通常の調味料よりも塩分が少ないため、有効です。ただし、減塩だからといって量を増やしてしまうと意味がありません。通常の調味料と同様に、適量を使うことが大切です。
塩分をコントロールして、健康な未来を手に入れよう
塩分を控えることは、一時的なダイエットや健康法ではなく、一生をかけて続けるべき、自分自身への大切な投資です。 高血圧や心臓病、脳卒中、腎臓病など、多くの病気のリスクを減らすことができます。
今日からできる小さな一歩を始めてみませんか?
食事の際、醤油やソースは「かける」のではなく「つける」 ・インスタント食品や加工食品の「塩分量」をチェックする ・だしのうま味や香辛料、ハーブを積極的に使う
毎日の食生活を見直すためのヒント
 健康的な食生活を送るためには、日々の意識が鍵となります。以下のような対策が有効です。
健康的な食生活を送るためには、日々の意識が鍵となります。以下のような対策が有効です。
野菜を「もう一皿」プラス: 1日の野菜の目標摂取量350gを達成するためには、あと小鉢1皿分(約70g)の野菜が必要です。朝食や昼食での野菜摂取量が少ない傾向にあるため、意識的に取り入れてみましょう。
「野菜ファースト」を実践: 食事の最初に野菜を食べることで、血糖値の急激な上昇を抑える効果が期待できます。外食や総菜利用時の工夫: 外食や調理済み食品を利用する頻度が高い人ほど、食塩摂取量が多くなる傾向があります。メニューを選ぶ際には、栄養成分表示を参考にすることも大切です。
健康な生活は日々の食生活から作られます。今回の調査結果を参考に、できることから少しずつ健康的な食生活を始めてみませんか。
あなたの健康的な毎日を、心から応援しています。

さあ、今日から始める、未来の自分を健康にするための第一歩を踏み出しましょう。
参考記事
かかりつけ医をさがそう
◆岐阜県エリアの 病院・医院・介護施設がすぐに見つかるポータルサイト 医療&介護ガイドぎふ◆







