これは 「物忘れ?」それとも「認知症?」
娘:「あれ?お母さん、さっきも同じこと言ってなかった?」
母:「あら、そうだったかしら? もう、年かしらねぇ」
娘「でも、さっきお昼に食べたもの、何だったか覚えてる?」
母:「えーと、なんだっけ? 鶏肉…だったかなぁ。もう、全然思い出せないわ」

これは、もしかしたら皆さんのご家庭でも見られる、ごく日常的な会話かもしれません。
「ただの物忘れだろうか?」
「もしかして、認知症の始まりなのだろうか?」
こうした不安が、ふとした瞬間に心に重くのしかかることはありませんか?
認知症と加齢による物忘れは、どう違う?
「最近、物忘れがひどくて…」という悩みは、誰しもが抱えるものです。しかし、認知症は単なる加齢による物忘れとは根本的に異なります。
加齢による物忘れ
体験の一部を思い出せないことはあっても、その体験自体を忘れることはありません。例えば、「昨日の夕食に何を食べたか思い出せない」といった状況です。しかし、食後、冷蔵庫を開けて食材を見れば、「ああ、そうだった!」と記憶がよみがえることが多いでしょう。
認知症の症状
体験そのものを忘れ、さらに進行すると、思考や判断、そしてコミュニケーション能力など、生活全般にわたる認知機能が低下していく病気です。食事をしたこと自体を忘れて「まだご飯を食べていない」と訴えたり、慣れた場所で道に迷ったりすることがあります。
現在、日本は世界でも類を見ない超高齢社会に突入しており、それに伴い認知症と診断される方も増加の一途をたどっています。厚生労働省の推計では、2025年には65歳以上の高齢者の約5人に1人、つまり約700万人が認知症になると言われています。これは、決して他人事ではなく、誰もが関わりうる身近な問題なのです。
また、65歳未満で発症する「若年性認知症」も存在します。働き盛りの世代に影響を与える若年性認知症は、家計を支える大黒柱が罹患することで、経済的な問題や家族の生活基盤に大きな影響を及ぼすことがあります。そのため、社会全体での理解と支援がより一層求められています。
認知症の種類と、症状の特徴
認知症と一口に言っても、原因となる病気によっていくつかの種類に分けられます。それぞれの特徴を理解しておくことが、適切な対応につながります。
-
アルツハイマー型認知症:記憶から始まる変化
最も一般的なタイプで、脳の神経細胞が変性し、アミロイドβやタウといった異常なたんぱく質が蓄積することで発症すると考えられています。
- 初期症状: 新しい出来事を覚えられない「記憶障害」が最初に目立つことが多いです。「同じ話を何度も繰り返す」「物のしまい場所を忘れて、探し物が多くなる」「今日の日にちや曜日の感覚がなくなる」といった症状が見られます。
- 進行した症状: 日常生活に支障をきたすようになります。例えば、銀行でお金の計算ができなくなったり、簡単な調理ができなくなったりします。さらに進行すると、家族の顔が分からなくなったり、時間や場所の見当がつかなくなり、徘徊(はいかい)をすることもあります。
-
血管性認知症:脳の血管がもたらす「まだら」な症状
脳梗塞や脳出血など、脳血管の病気が原因で発症します。
- 初期症状: 脳の障害を受けた部位によって症状が異なるため、「まだら認知症」と呼ばれることがあります。例えば、記憶力は保たれているのに、歩行が不安定になる、といった症状が見られます。
- 進行した症状: 認知機能の低下に加えて、手足の麻痺、呂律が回らない、尿失禁といった身体症状を伴うことも少なくありません。また、感情のコントロールが難しくなり、急に泣き出したり、怒りっぽくなったりする「情動失禁」が見られることも特徴です。
-
レビー小体型認知症:見えないものが見える幻の世界
脳の神経細胞に「レビー小体」という異常な物質がたまることで発症します。
- 特徴的な症状: 一番の特徴は、「幻視(実際にはないものが見える)」です。「部屋に誰かいる」「子供が座っている」といったリアルな幻覚に悩まされることがあります。幻視は本人にとっては現実であるため、否定せずに寄り添うことが大切です。
- その他の症状: パーキンソン病のような手足の震えや筋肉のこわばり、歩行困難といった運動機能の障害を伴うことや、睡眠中に奇声をあげたり、暴れたりする「レム睡眠行動障害」もよく見られます。
-
前頭側頭型認知症:性格が変わったように見える変化
脳の前頭葉や側頭葉が萎縮することで発症します。
- 特徴的な症状: 社会的なルールやマナーを守れなくなる「社会性の欠如」が目立ちます。例えば、万引きを繰り返したり、所構わず大声を出すなど、これまでとは全く異なる行動を取ることがあります。これは本人の意思によるものではなく、病気が原因であることを理解することが重要です。
- その他の症状: 同じ行動を繰り返す「常同行動(毎日決まった道を散歩する、特定のものを集めるなど)」も特徴的です。また、言葉がうまく話せなくなる「失語」の症状が現れることもあります。
「もしかして?」と感じたときの具体的な対応策
もし、ご家族やご自身に「もしかしたら認知症かも」と思うような症状が見られたら、一人で悩まず、早期に専門家や医療機関に相談することが何よりも大切です。
もしかして? と感じたら
ご自身や大切なご家族の様子を見て、「あれ?」「もしかして?」と感じたことはありませんか?
認知症のサインは、誰にでも起こりうる単なる物忘れと見分けがつきにくいことがあります。このチェックリストは、あくまでも初期の兆候に気づくための目安です。以下の項目に複数当てはまる場合、専門家への相談を検討するきっかけにしてください。
日常生活で気づく変化チェックリスト
以下に挙げる項目は、認知症の初期にしばしば見られる行動や言動の変化です。当てはまるものがあれば、チェックを入れてみましょう。
記憶に関する変化
- 📞 最近のできごとや約束を頻繁に忘れるようになった。
- 💬 同じ話を何度も繰り返すようになった。
- 👛 大切なものを置き忘れたり、失くしたりすることが増えた。
- 🗓️ 今日の日付や曜日、季節がわからなくなった。
- 👨👩👧👦 家族の名前や顔がわからなくなることがある。
思考・判断に関する変化
- 🔢 お金の計算や、買い物の合計ができなくなった。
- 🍳 料理の手順を忘れたり、味付けを間違えたりすることが増えた。
- 🏠 慣れているはずの場所で道に迷うことがあった。
- 📞 電話やメール、リモコンなど、今まで使えていた機器の操作が難しくなった。
- 🚦 危険な状況(火の消し忘れ、道路への飛び出しなど)に気づきにくくなった。
性格や行動に関する変化
- 😔 些細なことで怒ったり、悲しんだり、感情の起伏が激しくなった。
- 😥 今まで好きだった趣味や外出を嫌がるようになった。
- 🚿 身だしなみを気にしなくなり、清潔感が保てなくなった。
- 🤫 周囲への関心が薄れ、人との交流を避けるようになった。
- 🗣️ 会話中に適切な言葉が出てこず、会話が途切れることが増えた。
チェックリストの結果と、その次の一歩
もし上記のチェックリストに複数の項目が当てはまったとしても、それがすぐに認知症であると断定できるわけではありません。しかし、それは脳からの重要なサインかもしれません。
- かかりつけ医に相談する
- まずは、日頃から健康状態を把握してくれているかかりつけ医に相談してみましょう。
- 地域包括支援センターに相談する 地域包括支援センターは、高齢者の暮らしを地域で支えるための総合相談窓口です。保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員といった専門職が連携して、認知症の相談にも応じてくれます。医療機関の紹介や、介護保険制度の利用に関するアドバイスなど、様々なサポートを受けることができます。
- 「もの忘れ外来」を受診する もの忘れ外来は、認知症の専門的な診断や治療を行う医療機関です。CTやMRIなどの画像診断や、心理検査などを行い、認知症であるかどうか、またその種類や進行度を正確に診断します。
「新しい認知症観」で、希望ある未来へ
2024年に施行された「認知症基本法」では、「新しい認知症観」が提唱されています。これは、「認知症になっても、尊厳が保たれ、自分らしく希望を持って暮らせる社会」を目指すという考え方です。
認知症は、残念ながら治る病気ではありません。しかし、適切なケアと周囲の理解があれば、穏やかに、そして自分らしい生活を送ることは十分に可能です。大切なのは、病気と向き合い、その人らしさを尊重しながら、共生していくことです。
今日からできる認知症予防
認知症を完全に予防することは難しいとされていますが、発症リスクを下げたり、進行を遅らせたりするために、日々の生活習慣を見直すことは非常に重要です。
- バランスの取れた食事: 野菜や魚、大豆製品などを中心とした、バランスの良い食事を心がけましょう。
- 定期的な運動: ウォーキングや水泳など、無理のない範囲で継続的な運動を習慣づけましょう。
- 社会的な交流: 趣味のサークルやボランティア活動など、積極的に人と交流する機会を持ちましょう。
- 頭の体操: 読書や将棋、パズル、新しい趣味を始めるなど、脳に刺激を与える活動を続けましょう。
- 質の良い睡眠: 十分な睡眠を確保し、疲労をためないようにしましょう。
これらの習慣は、認知症だけでなく、様々な病気の予防にもつながります。
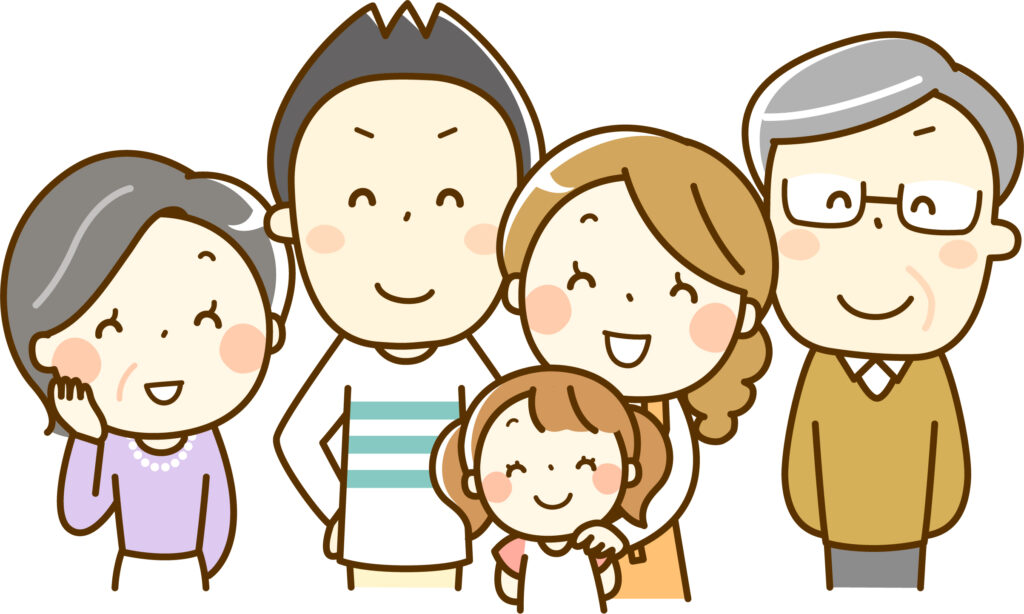
認知症は、決して特別な病気ではありません。誰もがなりうる可能性があり、誰もが関わる可能性のある身近な問題です。
大切なのは、正しい知識を持ち、過度に恐れることなく向き合うこと。そして、困ったときに一人で抱え込まず、専門家や周りの人々に頼ることです。
かかりつけ医をさがそう
◆岐阜県エリアの 病院・医院・介護施設がすぐに見つかるポータルサイト 医療&介護ガイドぎふ◆







